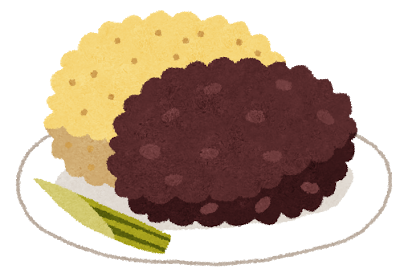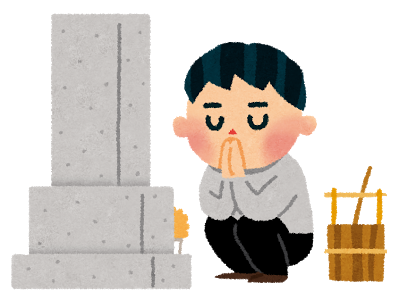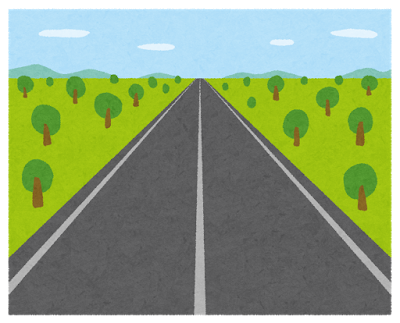お彼岸になると仏壇にお供えする「おはぎ」や「ぼたもち」。
名前はよく聞くけど、「どっちが春でどっちが秋?」「つぶあんとこしあんの違いってなに?」と、ふと疑問に
思うことはありませんか?
この記事では、お彼岸のお供え物としての意味や、ぼたもちとおはぎの違い、あんこの種類まで、やさしく丁寧にご紹介します。
季節の行事にまつわる知識を深めて、心を込めた供養をしてみませんか?
ぼたもちとおはぎの基本知識
ぼたもちとは?その特徴と歴史
「ぼたもち」は春のお彼岸に食べられることが多く、名前の由来は春に咲く「牡丹(ぼたん)」の花にちなんでいます。
もち米を軽くつぶして丸め、あんこで包んだ和菓子で、家庭でも手軽に作られる親しみのある存在です。
古くは江戸時代から食べられていたといわれ、ご先祖さまへの感謝の気持ちを込めた食べ物として大切にされてきました。
おはぎとは?由来と特徴
「おはぎ」は秋のお彼岸にいただくことが多く、こちらは秋の花「萩(はぎ)」にちなんだ名前です。
基本の材料や作り方はぼたもちとほぼ同じですが、形が少し細長く、あんこの種類や見た目で季節を感じられるのが魅力。
萩の花のように、素朴でやさしい印象があるのも特徴です。
ぼたもちとおはぎの違いは?
一番の違いは、呼び名と季節。
春に作られるのが「ぼたもち」、秋に作られるのが「おはぎ」とされており、季節の花にちなんだ名前で呼ばれています。
また、ぼたもちにはこしあん、おはぎにはつぶあんを使うことが多いという違いもあります。
このあんこの使い分けにも意味があり、季節感や素材の状態によって選ばれるんですよ。
お彼岸に食べる理由
ぼたもちやおはぎをお彼岸に食べる理由は、「小豆(あずき)」の赤い色が邪気を払うと信じられていたからです。
仏様やご先祖さまに感謝しながら、家族みんなで分け合っていただくことで、心が穏やかになるといわれています。
また、昔は高級品だったあんこを使って感謝の気持ちを表すという意味合いもあります。
春と秋のお彼岸の違い
春のお彼岸は春分の日を中心に、秋のお彼岸は秋分の日を中心に、前後3日間ずつ、計7日間あります。
春は「自然の恵みに感謝する日」、秋は「実りへの感謝と祖先供養の日」とされ、同じ“お彼岸”でも微妙に意味合いが異なります。
どちらも心静かに手を合わせ、ご先祖さまを偲ぶ大切な期間です。
お彼岸のお供え物としての位置付け
お供え物の基本と意味
お彼岸のお供え物は、仏さまやご先祖さまへの感謝の気持ちを表すものです。
特に手作りのおはぎやぼたもちは、手間をかけて作ることで心を込めた供養になるといわれています。
あんこの甘さやもち米の温かさには、優しさや愛情が込められているんですね。
おはぎとぼたもち、どちらが好まれる?
地域や家庭によって好みが分かれますが、秋のお彼岸には「おはぎ」、春には「ぼたもち」が選ばれることが多いです。
ただ最近では、あんこの種類や食べやすさから、どちらの名前でも通じるようになってきていて、あまり厳密に区別されなくなってきました。
お彼岸以外での食べられ方
お彼岸以外でも、法事やお墓参り、お盆などの供養の場面でおはぎやぼたもちが登場することがあります。
また、スーパーや和菓子屋さんでも季節を問わず販売されていて、おやつとして楽しむ方も増えています。
昔ながらの和の味として、幅広い世代に愛されています。
おはぎとぼたもちの材料と作り方
あんこの種類と選び方(つぶあん・こしあん)
つぶあんは小豆の皮が残っていて、食感が楽しめるのが特徴。
秋に実がしっかりと育った小豆が使われることから、おはぎにはつぶあんが多く使われます。
一方、春はまだ皮がかたいことが多いため、なめらかなこしあんが使われることが一般的です。
どちらを選ぶかは、好みや作る時期に合わせて選ぶといいですね。
作り方の基本手順
1.もち米を炊いて、軽くつぶす
2.小さく丸める(または楕円に)
3.あんこを外側にまぶす、または中に入れる
とってもシンプルな工程なので、お子さまと一緒に作っても楽しいですよ。
手作りならではの温かみが感じられます。
地域ごとの違い(西日本、東日本)
西日本では、きなこや青のりをまぶしたものも人気があり、あんこ以外のバリエーションも豊富です。
一方、東日本ではつぶあんやこしあんが主流で、比較的シンプルな仕上がりが好まれる傾向にあります。
こうした地域差も、和菓子の楽しみのひとつですね。
おはぎとぼたもちのための材料相場
もち米やあんこはスーパーで手に入りやすく、手作りの場合は1人前あたり100~150円ほどで作れるのも嬉しいポイント。
市販の和菓子店で購入する場合は、1個150~300円ほどが相場です。
価格帯を知っておくと、手作りするか購入するかの参考になりますよ。
お供え物の準備と供養のマナー
仏壇への供え方と供養の意義
おはぎやぼたもちをお供えする時は、きれいなお皿にのせて仏壇の中央に置きます。
供えたあとは家族で一緒に手を合わせ、いただくことで供養の心が届くとされています。
毎年の習慣として行うことで、自然と家族の絆も深まっていくんです。
家族での供養の重要性
お彼岸は、家族で一緒にご先祖さまを想う時間を持ついい機会です。
小さなお子さんにも、ぼたもちやおはぎを通じて「感謝の気持ち」や「命のつながり」を伝えるきっかけになります。
家庭でのあたたかい供養が、心を育てる時間にもなりますよ。
秋分の日・春分の日の供養の意味
春分の日や秋分の日は、昼と夜の長さが同じになり、「彼岸と此岸(しがん)が最も近づく日」ともいわれています。
この日を中心にお彼岸の行事を行うことで、ご先祖さまとの心の距離もぐっと近づくと考えられています。
季節の節目に、あらためて命や自然に感謝するきっかけになりますね。
まとめ
お彼岸にいただく「ぼたもち」や「おはぎ」は、見た目も名前もよく似ていますが、季節やあんこの種類によって違いがあります。
それぞれに込められた意味や歴史を知ることで、いつもより深く供養の心を感じられるかもしれません。
この記事では、お供え物としての位置付けや作り方、供養のマナーまでやさしくご紹介しました。
ご先祖さまへの感謝を込めて、今年のお彼岸は心を込めて準備してみてくださいね。